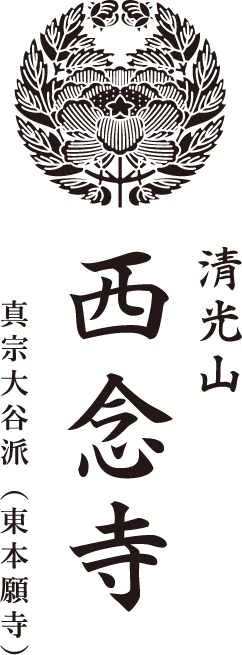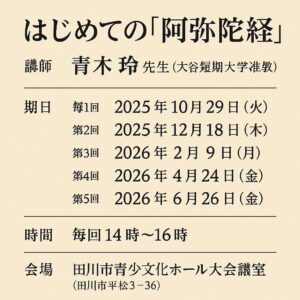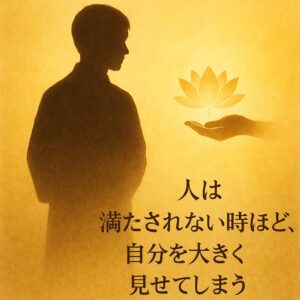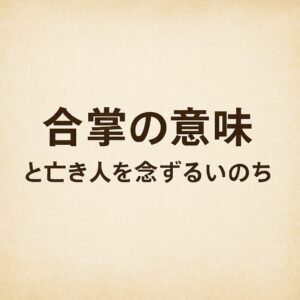先日、九十歳を迎えられた御門徒のおばあちゃんとお話をしておりました。その中で、心に残る一言がありました。
「うちの主人と義父はね、食事のあとになると、囲炉裏の灰に字や矢印を描いて、よう仏法を語り合いよったとよ。」
その姿を思い浮かべたとき、私は胸が熱くなりました。湯気の立つちゃぶ台の横、囲炉裏の火がゆらめく中で、お二人は仏法を語り、聞き合い、確かめ合っておられた。それは、まさに法の火を囲む談合の場だったのだと思います。
福岡県田川郡香春町・鏡山の「呉(くれ)」という地域は、昔から聴聞の熱い土地でした。法話があると聞けば、夜でも足を運び、翌日にはその話を囲炉裏端で語り直す――そんな日常が息づいていたと聞きます。
蓮如上人は「談合せよ」とお勧めになりました。法話を聞いたなら、ただうなずくだけで終わらせず、「自分はこう聞いた」「ここがようわからん」と、互いに語り合い、確かめ合うことが大切だと教えられました。
「談合なき聴聞は、風に吹かれる灯のごとし。」
どれほど良い法話を聞いても、語り合わなければ、その法の灯はすぐに消えてしまう。談合は、灯を風から守り、その光を自分の心に移す大切な時間だったのです。
けれど、時代の流れの中で、その囲炉裏も姿を消し、談合の声も聞かれなくなっていきました。いま思うと、それは土地が蓄えてきた法の熱が少しずつ冷めていく過程でもあったのかもしれません。住職として、その流れを止めることができなかった悔しさがあります。あの囲炉裏の火を、どうにかもう一度灯したい――そんな思いが、この胸の奥で消えずに燃え続けています。
けれど同時に、思うのです。あの囲炉裏の火は、完全に消えたわけではない。その火を見ていたおばあちゃんの記憶の中に、そして、その話を聞かせていただいたこの私の心の中に、確かに燃えている。
談合とは、昔の風景ではなく、いのちといのちを温め合う「法の対話」の場です。今はもう囲炉裏はなくても、パソコンの光の前でこうして語り合う時間の中に、あの火のぬくもりを感じることができます。
呉の地に受け継がれたその信心の火を、次の世代へとつないでいくこと――それが、今を生きる私に与えられた課題だと思っています。
南無阿弥陀仏
西念寺・関連ページ
所在地:福岡県田川郡香春町(鏡山・呉)