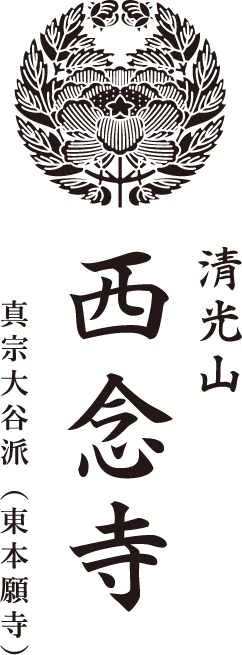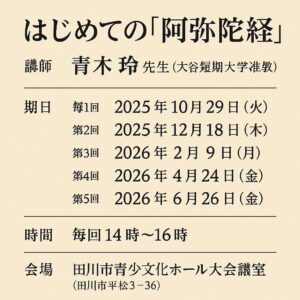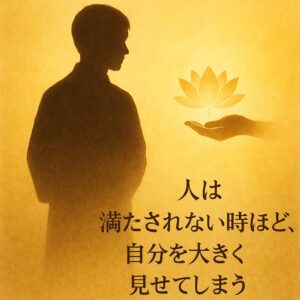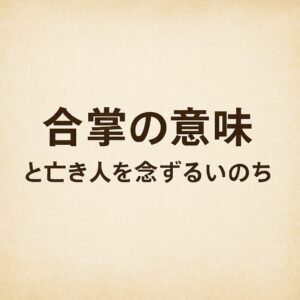田川郡大任町「道の駅ふれあい広場」での気づき
田川郡大任町の「道の駅ふれあい広場」へ、息子を遊ばせに行きました。下の娘(2歳半)が昼寝をしている間のひとときです。
先週の日曜日は一日中お参りがあり、息子をどこにも連れて行けませんでした。家の中で遊んでいても下の娘に邪魔をされ、つい押し倒してしまい、妻に叱られる――そんな出来事がありました。その日の夕方、お風呂に入る時も元気がなく、どこか沈んだ様子でした。
そして翌日の月曜日、「学校に行きたくない」と言い出し、学校に行っても先生の指示に従わず、機嫌が悪かったようです。
親の心にも映し出される「因縁」
子どもの機嫌の裏には、必ず理由があります。「叱られたから」「遊べなかったから」と表面的に見える出来事の奥に、もっと多くの“因と縁”が重なり合っています。「遊びたかった」「甘えたかった」「見てほしかった」――そんな願いが叶わなかった時に、子どもは反発や不機嫌という形で心を表します。
そして、子どもの心が乱れると、親の心もまた乱れます。息子が不機嫌だった月曜日、私はお参り先の門徒さんから「お疲れですか」と心配され、妻も、息子を学校に送った時に「お母さん、今日疲れてないですか」と尋ねられたそうです。家族全体に、どこか“影”のようなものが落ちていたのでしょう。
それもまた、「一つの出来事が次の出来事を生み出す」という因縁のはたらきです。子の不機嫌が親の心を曇らせ、親の疲れがまた子へと返っていく。まさに、互いに縁となって生きている姿です。
「育てる」とは、「育てられる」こと
私たちはつい、「子どもをどう育てるか」と考えがちですが、実は、子どもとの関わりを通して自分自身が育てられています。思いどおりにならない出来事を通して、「自分もまた、思いどおりにならない存在であった」と気づかされる。その気づきこそ、仏法の光に照らされた瞬間です。
子どもの不機嫌も、親の疲れも、決して“悪いこと”ではなく、私たちが因縁の道理を見つめ直し、思い通りにならない状況を徳に転じる如来の働きを仰ぐ、大切なご縁なのだと思います。