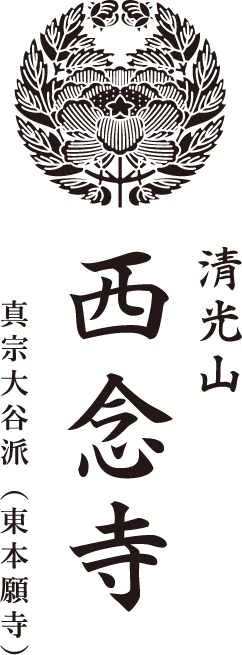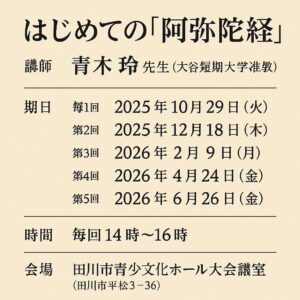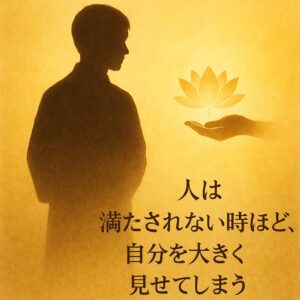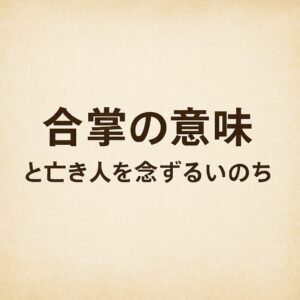ある日のことでした。本堂の耐久年数について、建築の専門家である総代さんがこう言われました。「しっかり管理していけば、あと三、四十年は大丈夫。百年はもつでしょう。」
その言葉を聞いて、私は思わず「ありがたいなぁ」と安堵しました。けれど同時に、ふと寂しさもこみ上げてきたのです。「百年もつなら、私は新しい本堂を見ることはできないなぁ」と。
そんな話を、後日ご法友に何気なくこぼしました。すると、その方が少し微笑みながら言われたのです。
それでいいんじゃないですか。自分が見るためじゃなく、次の人が手を合わせられるように残している。それが本堂を預かるということじゃないですか。
その一言に、はっとしました。私はいつのまにか「建物を残す」ことにばかり心を向けていたのです。けれど、ほんとうに大切なのは、念仏の場を受け渡していくことだった。するとご法友が、さらにこんなたとえ話を紹介してくれました。
老木は新芽を見ず、新芽は老木を知らず。けれど、根は一つなんですよ。
その言葉が胸に深く染み込みました。私は新しい本堂を見ることはできなくても、その「根」の一部として今を生きている。そして、いま手を合わせるこの場所も、かつての住職やご門徒の方々が「私たちのために」残してくださった本堂なのだと気づかされました。
見えぬ未来へと願いを送り、いつか咲く花を信じて、いまの根を守り育てる――それが、寺を預かる者の務めであり、ご法友が教えてくれた「老木の生き方」なのだと思います。
※出典不詳。「老木は新芽を見ず…」の句は、縁のつながりを説く比喩として広く用いられる言葉です。