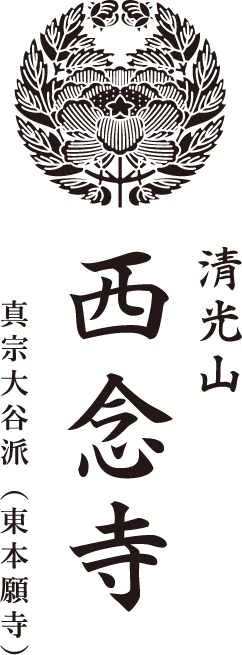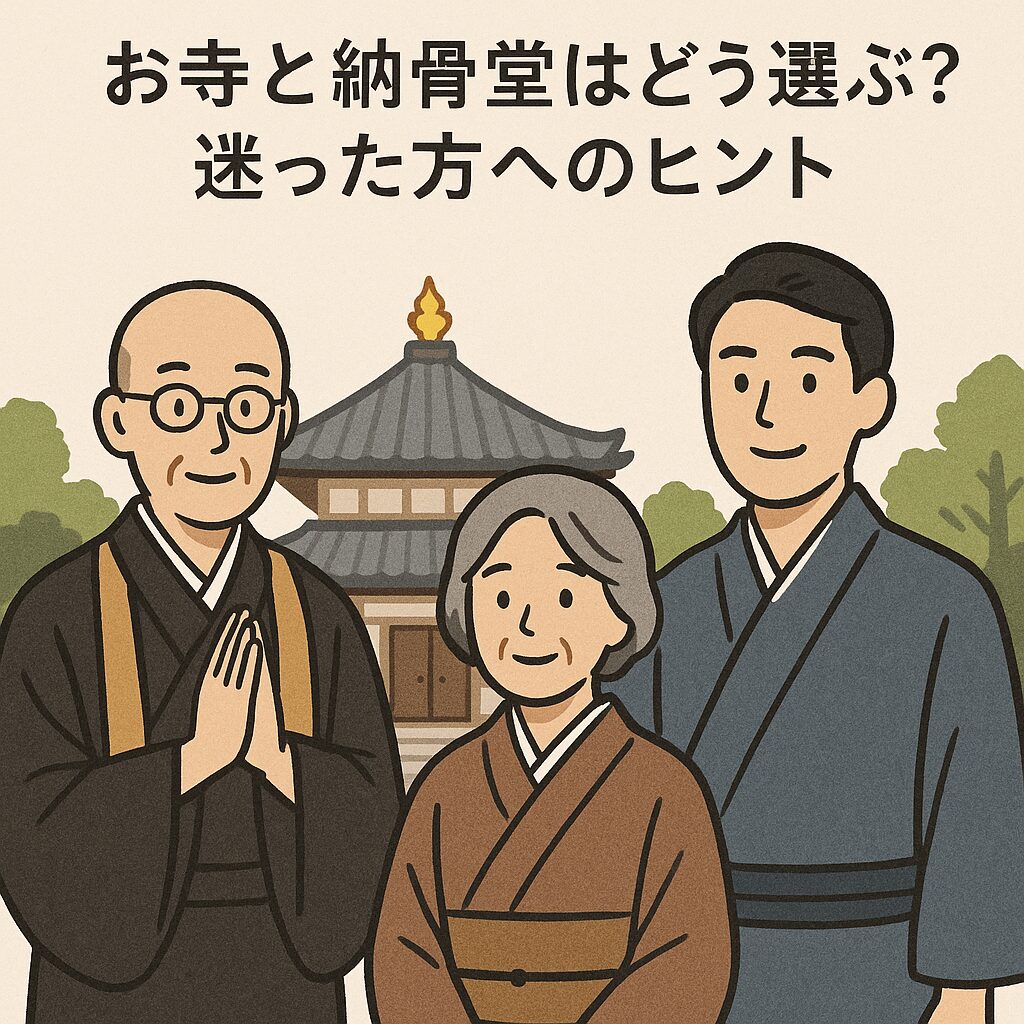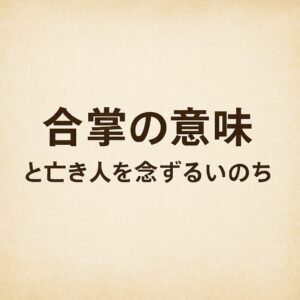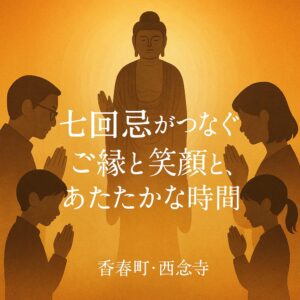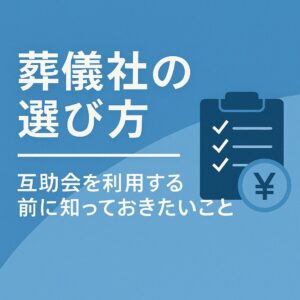近年は、跡取りでない次男や三男の方、あるいは都会に出ていた方が地元に戻ったときに、
「どこのお寺にしようかな」「どこの納骨堂にしようかな」
と、インターネットや広告を見ながら、お寺や納骨堂を“選ぶ”場面が増えてきました。
「自宅から近いところがいいかな」「きれいで明るそうな納骨堂がいいな」
といった、いわゆる“条件”で比べていくのは、今の時代では自然な流れだと思います。
私もそれ自体を頭ごなしに否定するつもりはありません。
むしろ、新しく建てた自宅の近くのお寺や納骨堂にご縁を結ぶことは、
私自身も大切な選択肢だと思っています。
距離が近ければ、日常のご挨拶もしやすく、急な仏事や相談ごともスムーズです。
共働きや核家族が増えた今、「近さ」は安心につながる大きな要素です。
また、「どんな住職さんがいるのか」という視点も、とても大切だと感じています。
住職の人柄や姿勢ひとつで、仏事や日々のご相談の受け止め方は大きく変わります。
しっかり向き合ってくれる住職に出遇えたなら、それは確かに良い仏縁となり、
ご自身の人生の支えにもなっていくでしょう。
ですから、
「近さ」「通いやすさ」に加えて、「どんな住職さんか」という点も、
お寺や納骨堂を選ぶうえで、ひとつ大事な要素だと思います。
もちろん、「住職でお寺を選びなさい」という話ではありませんが、
せっかくなら、安心して話せる方とご縁を結んでいただきたい――
そのように思うのです。
こうした意味で、
「条件でお寺や納骨堂を比べて選ぶこと」自体は、決して悪いことではありません。
ただ、その一方で、もう一つだけ、心に留めておいてほしい視点があります。
それが、
「親や祖父母と同じお寺に通うこと」
「ご先祖と縁のあるお寺の納骨堂におさまること」
には、目には見えない大切な意味があるのではないか、という視点です。
■ お寺は“法事を依頼する場所”ではなく、家族の歴史を覚えている場所
本日、三十三回忌の法事がありました。
私はまだ学生の頃で、故人には直接お会いしておりません。
しかし、お寺の内側では、自然とこんな会話が交わされます。
「どんな方やった?」
「しゃべり好きの、明るい方やったね。」
「ようお寺にお参りされよった。」
「一緒に四日市別院にもお参りに行ったことがあったよ。」
住職である私が直接お会いしていなくても、
お寺の中にはその方を覚えている人がいて、
故人の姿や温かい思い出が語り継がれていきます。
お寺とは、
亡くなられた方の“記憶”がそっと守られ、
次の世代へ受け渡されていく場所でもあります。
また、代々同じお寺とご縁が続いていれば、
故人の兄弟や親族とのお付き合いも自然と続いていくものです。
実は先日、幼い頃に大好きだった御門徒のお爺ちゃんの話を、
40年越しに、その甥御さんから改めて聞くという出来事がありました。
その記事はこちらです:
幼い頃に大好きだった御門徒のお爺ちゃんの話
こうした「家族の記憶が継承されていく場所」であることは、
単なる利便性では決して得られない、お寺の大切な役割です。
■ 山の炭と、本堂の床下の記憶
ちょうど先日、二年前から仏事が復活した門徒さんが、何気なく話してくださいました。
「実は父が、生前ずっと、お寺の山を無償で手入れしていたんですよ。」
さらに伺うと、
山の木を伐り出し、炭にまで焼いて、お寺に持ってきてくださっていたそうです。
その話を聞いたとき、私は子どもの頃の記憶がよみがえりました。
当時は灯油ストーブが普及し始めていたものの、境内には鉢形の囲炉裏があり、炭も焚いていた時代でした。
本堂の床下には、炭がたくさん積まれていた光景を、私は今でもはっきり覚えています。
「あの炭は、まさにあの方が山から切り出し、時間をかけて焼いて、
お寺に届けてくださったものだったのだ」と思ったとき、
胸がじんわりと熱くなりました。
お寺はただ“建物”としてそこにあるのではありません。
何十年、何世代にもわたって支えてくださった方々の手間と温かさによって、
守られてきた場所なのだと、改めて思い知らされました。
そのお寺の本堂の下に眠るご先祖、
そのお寺の納骨堂におさまるご遺骨には、
そうした“支え合いの歴史”も一緒に息づいているのだと思います。
■ 何十世代と続いてきた“ご縁の重み”
こうした“ご縁”は、一代や二代だけの話ではありません。
田舎のお寺には、
十代、二十代、あるいは三十代と続いてきた家も少なくありません。
互いに助け合い、支えられながら歩んできた長い歴史があります。
代々のお寺には、ご本人だけでなく、
ご兄弟や親族とのお付き合いが続いていくという強みもあります。
法事のたびに、「お兄さんはこういう方でしたね」「お母さんと一緒によくお参りされていましたよ」と、
故人やご親族の姿が自然と語られるのです。
私自身、幼い頃から大好きだった御門徒のお爺ちゃんがいました。
その方が亡くなられて四十年近くたって、甥御さんから戦争中のお話や人柄の奥行きを伺い、
胸に迫るものがありました。 このように、別の世代から故人の姿を聞けるのも、長いご縁が続いてきたからこそです。
代々の方々が「ここで手を合わせてきた」という積み重ねは、
目には見えませんが、現代の合理的な選択だけでは決して作り出せない“深い重さ”を持っています。
そこには、 「このお寺なら安いから」「この納骨堂は設備が新しいから」といった比較ではありません。
長い時間をかけて編まれてきた、“ご縁”という目に見えない糸があります。
■ 一時の感情や事情では断ち切れないもの
代々のご縁には、本人ですら気づいていない深さがあります。
それを教えられた出来事が、私の周りにもいくつかあります。
あるとき、私の対応に不満を持ち、 「もう月参りは結構です」と、お断りに来られた方がいました。
たまたま応対したのは、九十代後半の前坊守でした。
前坊守は、事情を知らぬまま静かにこう申し上げたそうです。
「昔はね、車もバイクもない時代でね。 あなたのお家まで、1時間かけて歩いてお参りに行っていたのよ。」
その一言を聞いて、 「自分は何を断とうとしていたのか」とハッとされたそうです。
代々のご縁を、一時の感情で断とうとしていた自分に気づかれ、 改めて月参りに戻って来られました。
また、他寺のお話ですが、経済的に非常に苦しくなり、 「もうお月忌は続けられません」と断りに来られた門徒さんがありました。
そのとき、その寺の住職はこう言われたといいます。
「包めなかったら包めなくて構わん。 お布施がなくても、あなたのお家にお参りさせてもらえるなら、それでいいんですよ。」
門徒さんはその言葉に涙ぐみ、後にこう語っておられました。
「あの時期、お布施が出せなかったのに、 見捨てずにお参りに来てくださったことが、本当にありがたかった。」
そこには、 「ご縁はお金では切らない」という住職の姿勢がありました。 その姿勢によって、門徒さんの心が深く支えられたのだと思います。
■ 祖父が示した“ご縁を守る姿勢”
もう一つ、私の祖父のエピソードがあります。
ある方が、 「これからは西念寺に加わりたい」と相談に来られたことがありました。 元々通っていたお寺と、少し行き違いがあったためでした。
しかし祖父は、静かにこうお伝えしたといいます。
「あなたの家は長いあいだ、あのお寺を大切にしてこられました。
そのご縁は、そう簡単に手放すようなものではありません。
どうか元のお寺を大事にしてください。」
自分の寺に引き入れるのではなく、 その家が代々歩んできたご縁を尊重して返す――。 昔の住職には、そうした“縁を守る倫理”が自然にありました。
祖父の言葉を思い返すたびに、 家とお寺を結んできたご縁には、 個人の気持ちや、その場の都合だけでは動かせない歴史があるのだと知らされます。
■ 納骨堂を選ぶときに、もう一つだけ見てほしいこと
では、納骨堂を選ぶときには、何を大事にすればよいのでしょうか。
もちろん、
- 自宅や実家からの距離
- お参りのしやすさ(階段かエレベーターか、駐車場はあるか など)
- 管理体制(掃除や建物の維持はどうか)
- 将来、自分が高齢になっても通える場所かどうか
こうした“現実的な条件”を考えることは、とても大切です。
むしろ、そこをよく検討されるのは良いことです。
そのうえで、もう一つだけ、心に留めていただきたいのが、
「その納骨堂は、どこのお寺が責任をもってお守りしているのか」
「そのお寺とは、これからどんなご縁を育んでいけそうか」
ご実家がお世話になってきたお寺の納骨堂であれば、 そこには、これまでの家族の歴史や思い出がそのままつながっていきます。
また、たとえこれから新しくご縁を結ぶお寺の納骨堂であっても、 「この住職さん、このお寺なら安心して任せられる」 そう感じられるかどうかは、とても大切なポイントだと思います。
納骨堂は、“ご遺骨を保管する設備”以上のものです。 そこで手を合わせる家族を、何年、何十年と見守り続けていく場でもあります。
だからこそ、「建物のきれいさ」「費用の安さ」だけで決めてしまうのは、 少しもったいないように感じます。
■ 跡取りでなくても、親と同じお寺・納骨堂に通う意味
跡取りではない次男・三男の方や、都会から帰ってこられた方の中には、 「親や祖父母のお寺はあるけれど、自分は自分で別のお寺や納骨堂を選ぼうかな」 と考えられる方もおられるかもしれません。
もちろん、そのお気持ちもよく分かります。 暮らしている場所も、生活スタイルも、親の世代とは変わっています。
それでも私は、 親や祖父母と同じお寺に通い、 そのお寺が守っている納骨堂に手を合わせることは、 「自分がどこから来たのか」を確かめる大切な行為だと思っています。
それは単なる形式ではなく、 人生の基盤を思い出させてくれる“心のルーツ”に触れること。
だからこそ、 「お墓や納骨堂は親の代まで。自分は別でいいや」 と簡単に割り切る前に、 一度だけ立ち止まって、「うちの家とあのお寺とのご縁」を振り返ってみていただけたら―― そんな願いがあります。
■ まとめ 〜条件だけでなく、「ご縁」にも目を向けて
お寺や納骨堂を自由に選べる時代になりました。
そのこと自体は悪いことではありません。
むしろ、よく調べ、よく考えて選ぼうとされることは、とても大切なことです。
ただ、もしあなたの家が長いあいだ大切にしてきたお寺があるなら、
また、これから新たにご縁を結ぼうとしているお寺があるなら、
その「ご縁」というものにも、そっと目を向けていただけたら嬉しく思います。
広告やパンフレットには載ってこない「ご縁の重み」こそ、
これから生きる私たちを静かに、そして長く支えてくれる大切な力だからです。
福岡県田川郡香春町 西念寺